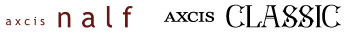キッチンを「お気に入り」に。
誰にでも自分の「お気に入り」ってありますよね。それが何であろうと、自分に元気をくれるもの。自分の生活が「お気に入り」で溢れれば、もっと生活を豊かに、楽しくできるはずです。
今回はご自宅のキッチンを自分の「お気に入り」にできる、こだわりの詰まった道具たちを紹介します。

まずは形から。
何に関しても、まずは形から入っていけばすんなりと趣味にできたりするものです。料理やお菓子作りに関しても、苦手意識だったりなんだか気分が乗らない…などでなかなか手が伸ばせない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回ご紹介する商品たちは、小さいながらもこだわりが沢山詰まったものばかり。キッチンの道具って、一度買うとそんなにすぐ買い替えたりしないので、始めに良い道具を揃えたいもの。一度道具に隠された便利な点を知ってみると愛着も湧いて、お料理やお菓子作りがすすむはずです。

conte まかないボウル 180 / 220
いつもは引出しのなかにひっそりとたたずんでいる「ボウル」。だけど、意外に出番は多いもの。 料理をされる方だったら、毎日のルーティンに必ず現れるのでは。
そんなさりげない「ボウル」を自分のお気に入りに。conteのボウルは形だって、性能だってとびきりです。
「世界一の研磨技術」新潟県燕市
燕市の金属加工業の歴史は17世紀初頭にまで遡ります。毎年のように起こる風水害に疲れてしまった燕市の住民たちを救うため、江戸から和釘の鍛冶職人を招き、農民の副業として和釘製造を奨めました。これが、燕鍛冶のはじまりとも言える出来事です。
つぎつぎに起こる「江戸の大火」で和釘の需要は増え、住民たちの鍛冶の技術がどんどん上がっていったという訳で、今現在にまでその技術が受け継がれてきています。
その鍛冶技術を用いてつくられたのがこの「conte まかないボウル」。「conte」というブランド名には
・con=コンテナ(container)で運ばれ、
長く使われ続ける(continue)道具でありたい
・te=沢山の職人の手と(hand)ともにつくる
こんな願いが込められています。

"まかないボウル"とは
この「まかないボウル」の語源ともなった「縁を巻かない」という工夫。昔のボウルによく見られるボウルは、ふちが巻かれてあり、そこに洗い残しが溜まり…乾かした後に、あれ?洗ったはずなのに残ってる!ということも。そもそも、ふちを巻いている意味とは何なのでしょう。
"縁"の重要性
その最大の理由は、強度を保つため。ですが、conteのボウルには縁が巻かれていません。なぜ巻かなくても強度が確保できるのか。スピニング加工をして縁に厚みをもたせているのです。その為、巻かれていなくても強度が保たれます。
また、ボウルは沢山揃えておきたいので同じサイズで重ねたりもします。その時に「取れなくなってしまった」という事もたまにあります。このまかないボウルは、ボディと縁の厚みが違うのでとっても取りやすいのも便利なポイント。
この細かい"縁"のポイントたちですが、実は研磨にとても手間がかかります。一般的な縁が巻かれてあるボウルだと、先部分を巻いて隠す事ができるのですが、まかないボウルだと隠す事ができないのでより丁寧な作業が求められます。ここで活躍するのが「新潟県燕市」の職人さんたち。小さなところにも手を抜かない、職人仕事に心躍ります。

深さがあるので混ぜやすい
普通のボウルに比べると、深さがあるのでとても混ぜやすい。わたしは、チョコレートなどを湯煎する際になかにお湯が入ってしまった経験がありました。ですが、このconteのボウルは高さがありますし、細長い形なのでお湯に面する面積もおおいのです。なので素早く湯煎する事ができます。
小さいサイズは、粉物や混ぜ物をする時に便利。料理をしていると意外に必要になるサイズです。

すくいやすく注ぎやすいレードル
先ほどご紹介した「conte」のボウルをつくっている所と同会社でつくられています。「すくいやすく注ぎやすいレードル」。このレードルはただかっこいいだけでなく、色んな点からとっても便利なレードルなんです。

おむすび形がポイント
このレードル、皿部分がおむすび形になっているのでとてもすくいやすく、注ぎやすい。ただ単におむすび形にしている訳ではなく、鍋底にフィットする角度を計算してつくられています。
鍋底にフィットするので、わざわざ鍋を傾ける必要がありません。重い鍋などを片手で持ち上げて、最後の一滴をすくおうとする時、手がすべって鍋の中身が全部こぼれそうになり、ひやっとする事があります。そんな危険性も避けられます。

左右対称で利き手関係なく使える
片方だけ注ぎ口があるレードルはよく目にしますが、両端にそそぎ口があるレードルは初めてです。ほんの少しの盲点を見つけて、改善した素敵なユニバーサルデザインです。スタイリッシュな見た目も嬉しいポイントです。

亀の子スポンジ
亀の子束子は約100年前、東京で生まれました。あの、よく見る「たわし」。それは亀の子束子が生んだ画期的な道具だったのです。そんな、歴史ある束子屋さんが生んだスポンジがこちらの「亀の子スポンジ」です。

抗菌作用がとにかく高い
抗菌性の銀イオンを使用しているので、とっても衛生的。スポンジに銀イオンを塗布するのではなく、練り込みを採用しているので、中心部から抗菌作用が働きます。菌が繁殖するのを防ぐ事によって、食中毒の心配もクリアになります。

水切れ・泡立ちがいい
スポンジの目を粗くする事によって泡立ちもよく、水切れも良いので、すぐに乾きます。触り心地もふんわりとしていて優しいのがポイント。

サイズにもこだわりが
このスポンジ、サイズにもこだわっています。一般的なスポンジが3cm〜4cmなのに対し、亀の子スポンジは2.7cmを採用。この厚みが女性には絶妙で握りやすいのです。

パッケージも素敵
この亀の子スポンジ、パッケージもとても可愛いですよね。実は、このパッケージデザインを手がけたのは菊池敦己さん。菊池敦己さんといえば、VI、ブランディング、アートディレクションなど色々なアートワークをされている方。青森美術館のVIやミナペルホネンのブランディング、丸亀市猪熊弦一郎美術館のカフェ運営など、名だたる施設やブランドのお仕事をされています。
また、商品開発にはミニマリストとして有名な石黒智子さんが協力しています。だからこのシンプルで潔いフォルムが生まれたのですね。わたしも納得のスポンジです。
期間限定カラーあるのが嬉しい
亀の子スポンジには期間限定カラーのスポンジも。例えば、今年の春は「桜」。以前は「コーヒー」「カフェオレ」なんて女性がきゅんとするカラーも。どんどんでてくるので、見逃せませんね。

こだわりのキッチンの品々。
ここまでご紹介してきた商品、一見シンプルですがつくられている会社の方々の思いが沢山詰まった商品ばかりです。
こんな思いの詰まった道具たちでキッチンが溢れれば、お料理やお菓子作りが楽しくなる事間違い無しです。この春に一度揃えてみてはいかがでしょうか。